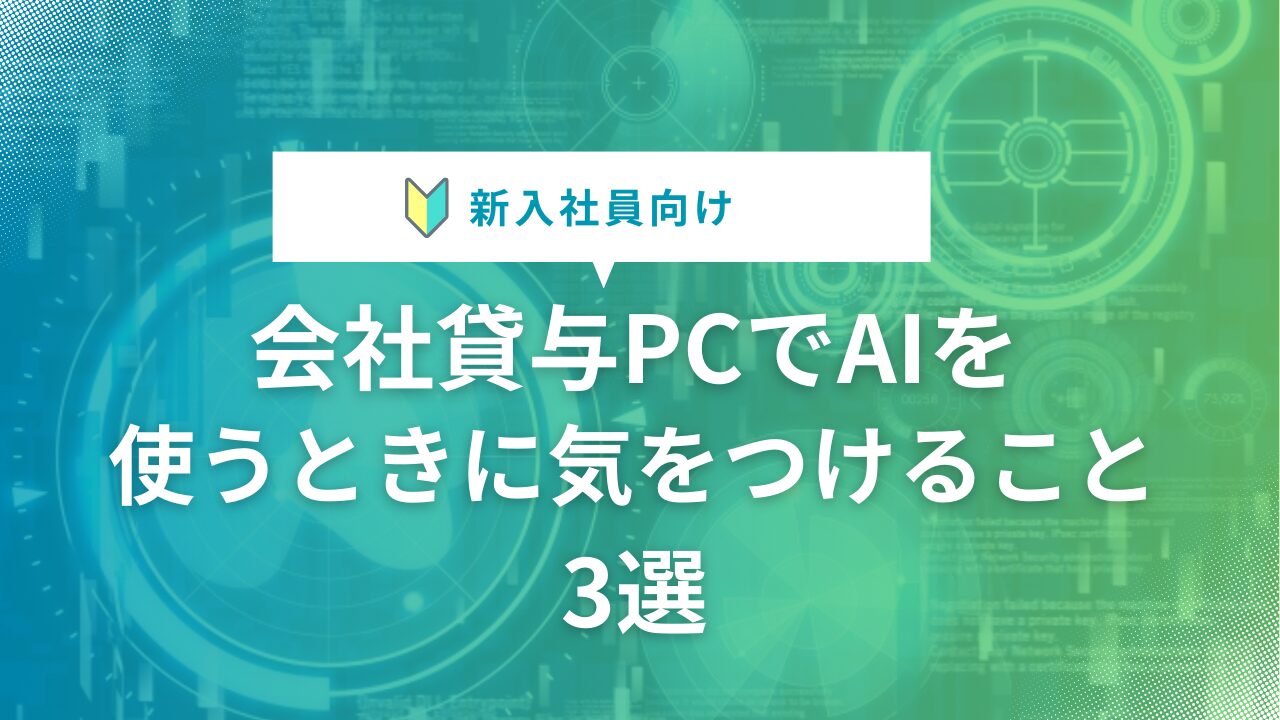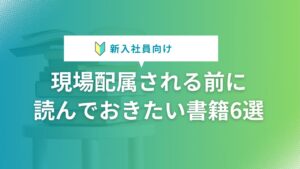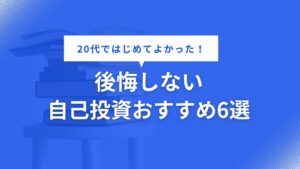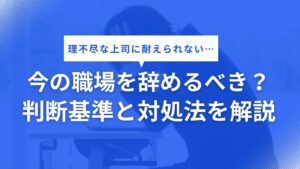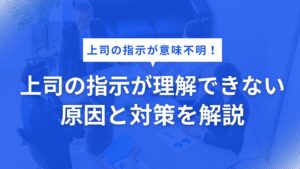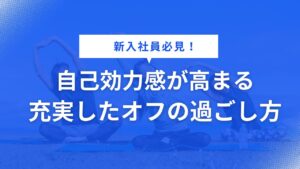近年のAIの進化は目覚ましく、会社でもAIを使用して業務を進めることが多くなりました。
議事録作成のために会議をレコーディングし文字起こしと要約をAIにお願いしたり、AIにソースコードを書いてもらったり、AIを使うことでできることの幅が大きく広がりました。
「大学の課題もchatGPTを活用していて使い方はマスターしているから会社でも活用しよう」
「会社の仕事をAIを使って爆速で終わらせよう」
会社に入ったばかりの方で、これからAIを活用したいと考えている方も多いのではないでしょうか。
しかし、会社では許可なくAIのツールを使用することができません。
企業や部署により、AIの使用についてルールを設けています。
この記事では、会社でchatGPTやCopilotなどのAIツールを活用している私が、気をつけたいことを解説します。
正しいルールを理解した上でAIを活用することで、信頼される社会人になりましょう!
会社では勝手にAIを使用してはいけない
AIツールは、会員登録すれば誰でも簡単に使うことができます。
会員登録せずに使用できるAIツールも多くなりました。
だからといって、会社に無断でAIを使用することはできません。
上司や先輩社員に相談し許可が出れば使用できますが、許可が出ない限りは使うことができません。
新人研修と現場配属でAI使用の方針が異なる場合がある
会社に入ると、多くの方が新人研修という研修を受けることになります。
企業により研修内容や研修期間は様々ですが、グループワークを1か月間行い、最終日に成果発表を行う企業もあるようです。
課題やグループワークを行う際に気になることの一つに、chatGPTのようなAIツールが使用できるかどうかではないでしょうか。
もし、新人研修中にAIツールを使用したい場面があった場合には、まず講師や新人研修を統括している人事部や総務部の方に使用して良いか相談しましょう。
使用して良いかどうかは企業により様々なため、実際に確認が必要になります。
また、注意しなければならないのは、新人研修と自分が実際に働く現場(部署)で、AIの使用方針が異なる場合が多いです。
新人研修ではAI使用OKでも、現場では新人のうちはAI使用NGなど、よくあります。
新人研修の場でのAI使用方針と現場でのAI使用方針は異なることを把握し、現場(部署)配属されたら改めてAIが使用できるか確認するようにしましょう。
会社でAIを使用するときに気を付けること3選
会社や会社から貸与されたPCでAIを使用する前に確認したいこと、使用する際に確認することを説明します。
AIを使用するときに気を付ける点は、次のとおりです。
- 社内規則や部署の方針を確認する
- 機密情報とは何かを理解し入力しないようにする
- AIを使用する前に上司に相談する
社内規則や部署の方針を確認する
AIツールの活用が進む中で、業務効率化や情報整理などに役立つ場面が増えています。
しかし、会社のPCでAIを使用する際は、まず社内のルールや所属部署の方針を必ず確認することが大切です。
なぜなら、AIの使用に関するルールは企業ごとに異なり、許可されていないツールの使用が情報漏洩やセキュリティ事故の原因となる可能性があるからです。
たとえば、ある部署ではChatGPTの使用が認められていても、別の部署では禁止されている場合があります。
また、会社によっては有料版AIの使用を制限しているケースもあります。
自分が使いたいツールが業務で利用可能か、事前に確認せずに使ってしまうと、思わぬトラブルを招くことにもなりかねません。
入社直後は、そもそもAIの使用が想定されていない環境である可能性もあります。
就業規則や情報セキュリティポリシー、部署内のマニュアルなどに目を通し、不明点があれば先輩社員や上司に相談しましょう。
正しいルールを理解した上で活用することが、安全で信頼される社会人への第一歩です。
機密情報とは何かを理解し入力しないようにする
AIツールを利用する際に特に注意すべきなのが機密情報の取り扱いです。
機密情報とは、社内の重要な情報であり、外部に漏れることで会社や取引先に大きな損害を与える可能性のある情報を指します。
機密情報の例
- 顧客の個人情報
- 未公開の製品情報
- 社内の売上データ
- 人事情報
- 取引先との契約内容
- 「社外秘」とある書類に記載された内容
これらの情報をうっかりAIに入力してしまうと、情報がAIの学習データに使われたり、外部に流出するリスクがあるため非常に危険です。
特に無料のAIツールは、どこまで情報が保存・再利用されるかが明確でない場合が多く、安全性の面でも注意が必要です。
「このくらいなら大丈夫」と自己判断は危険です。
「社外に出してはいけない情報とは何か」を理解したうえで、AIに入力する内容を厳選しましょう。
もし判断に迷う場合は、必ず上司や先輩社員に確認をとってください。
機密情報は、会社から貸与されたPCに限らず、私物のPCでAIツールを使用する際も入力してはいけません。
機密情報を守る意識を持つことは、信頼される社会人として欠かせない基本的な姿勢です。
AIを使用する前に上司に相談する
AIを業務で活用することは、仕事の効率化やアイデア出しに役立つ一方で、その使い方によっては問題が発生する可能性もあります。
新入社員のうちは、AIの利用について自己判断で進めるのではなく、必ず上司に相談することが重要です。
特に、業務で初めてAIツールを使う場合や、社内での使用ルールが明確でない場合には、事前に「このような目的で使いたいのですが、問題ありませんか?」と確認を取りましょう。
上司は業務内容や社内方針を把握しているため、適切な使い方や注意点をアドバイスしてくれるはずです。
相談を怠ると、意図せず社内ルール違反や情報漏洩につながるおそれもあります。
また、会社によっては有料版ライセンスを一括で管理していたりします。
使用する前に、社内特有の手続きが必要な場合もあります。
もしかしたら、有料版のAIツールを使用させてもらえるかもしれません。
上司としっかりコミュニケーションを取りながら、安全かつ効果的にAIを活用していきましょう。
AIが使用できないときの対処法
AIが使用できない背景には、セキュリティ上のリスクや情報漏洩の懸念、業務上の整合性の確保など、企業としての理由があります。
その理由を理解したうえで、無理に使おうとせず、ルールに従う姿勢を持ちましょう。
上司からの信頼を損なわないためにも、まずはルールを順守することが大前提です。
AIが使用できないと言われても会社に不満を抱いている場合ではない
現場や部署からAIを使ってはいけないと言われたみなさん、おめでとうございます。
みなさんには、ビジネスパーソンとして自分で考え抜いて成長する機会が与えられました。
AIが使用できない場合、まずはビジネスパーソンとしての基礎を習得してみるのはいかがでしょうか。
上司の方針によっては、新人のうちはNGだがある程度の仕事をこなせるようになったら使用を許可しよう、と考えている場合もあります。
AIの進化により、新人の仕事の代表であった議事録も、AIで自動で文字起こしや要約を行うことが可能となりました。
しかし、自分で議事録を作成することで、ビジネスパーソンとしての基礎スキルを身につけてほしいと考える上司はまだまだ多いようです。
また、AIに機密情報を入力してはいけないので、新人のうちは機密情報の判断がつかないだろうとしてAI使用禁止とすることもあるようです。
入社当初にAIの使用の許可が出なかった場合、まずはビジネスパーソンとしての基礎スキルを習得し、ある程度仕事ができるようにしましょう。
そうすると、会社でAIが使用できるようになる可能性が高いです。
社内ツールやナレッジを活用する
会社によっては、独自のナレッジデータベースや、チャットボット、マニュアル検索ツールなどが整備されている場合もあります。
まずは、社内ツールやナレッジを活用し、業務上の疑問や課題を自力で解決する姿勢を見せましょう。
「AIは使えなくても、自分で工夫して情報を探せる」というスキルは評価されやすいです。
出勤システムの操作や公共交通機関の遅延による遅刻の対処などは会社特有の問題となるので、chatGPTなどのAIツールに聞いても解決するのが難しくなります。
新人のうちは聞けば嫌な顔せずに教えてくれるかもしれませんが、年次が上がると聞いても教えてもらえなくなります。
AIが発達した今でも、自分で調べて解決するスキルも必要です。
先輩社員や上司からのインプットを積極的に得る
AIが使用できないときは、自分の思考力やコミュニケーション力を磨くチャンスととらえましょう。
分からないことを自分で考えたり、人に聞いたりして解決していくプロセスは、社会人の基礎力を鍛える良いトレーニングになります。
上司や先輩社員に質問する際も、質問するのに適したタイミングや質問前に準備した方が良いこともあります。
仕事内容を確認する際にも、仕事をスムーズに進めるためにいくつかのポイントを押さえる必要もあります。
AIに頼らない力は、どんな環境でも通用します。
まとめ AI使用時は規則をまもりAIが使用できなくても成長のチャンス
この記事では、会社や会社貸与PCでAIを使用する際に気を付けたいことをまとめました。
- 社内規則や部署の方針を確認する
- 機密情報とは何かを理解し入力しないようにする
- AIを使用する前に上司に相談する
AIを使用する際は、規則をまもり、機密情報は入力しないようにしましょう。
不明点がある場合は、上司や先輩社員に相談するようにしてください。
AIが使用できない場合は、社内ナレッジやツールを活用したり、上司や部署の人と積極的にコミュニケーションを取ったりしながら、仕事をすすめるようにしましょう。
今は使用できなかったとしても、後々使用できるようになる可能性もあります。