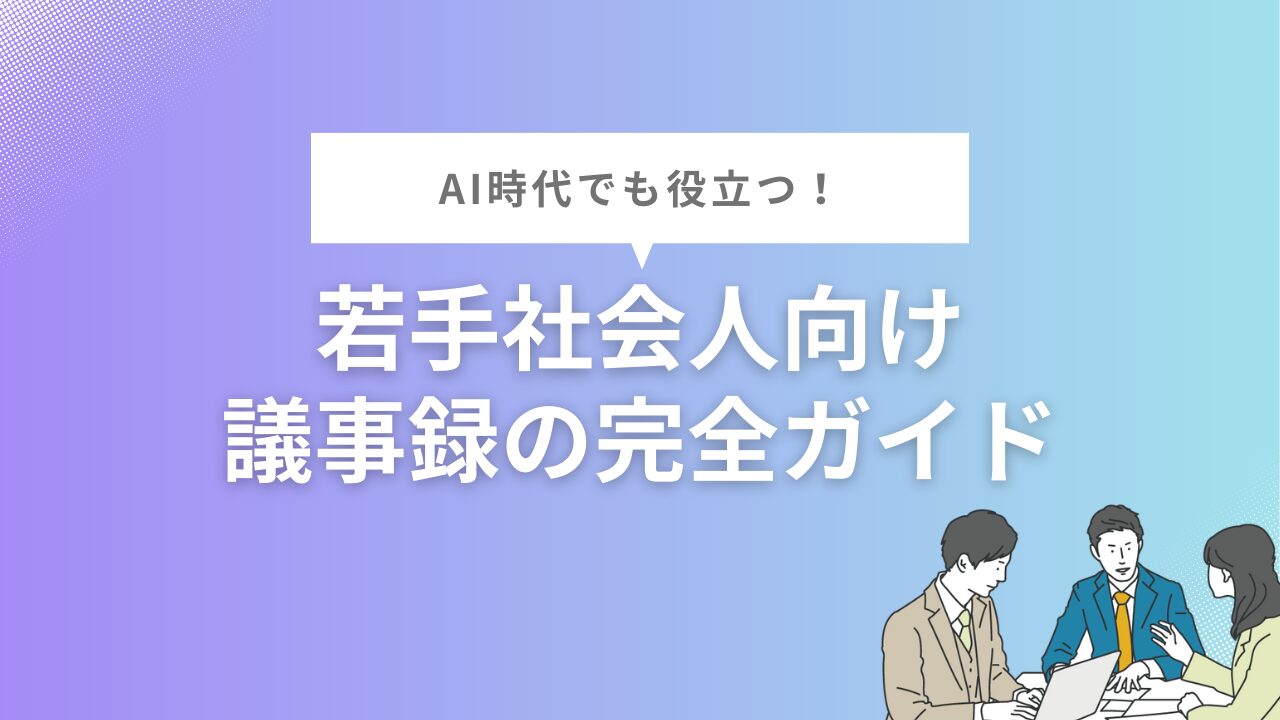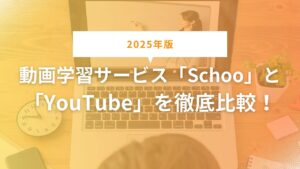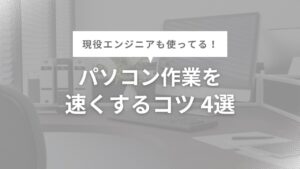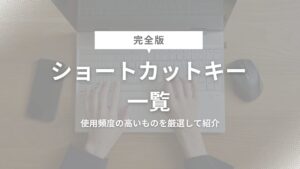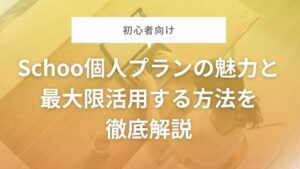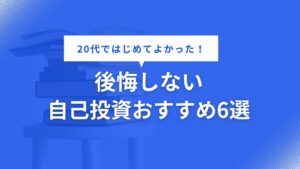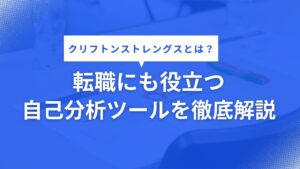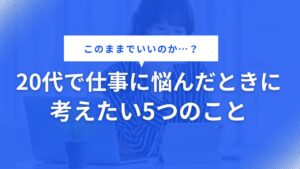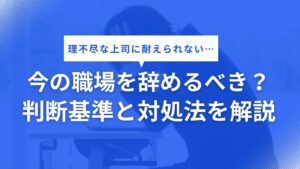社会人になって、最初に任されることのひとつに議事録作成があります。
「議事録ってただ会議の内容をメモすればいいんじゃないの?」と軽く考えていた人も、いざやってみると
「誰が何を言ったか全部書いてたら終わらない」
「要点をまとめたつもりが上司から『肝心なところが抜けてる』と指摘された」
など、議事録を作成することの難しさがわかります。
近年は、AIによる自動文字起こしツールも増え、議事録はAIに任せればいいのでは?と考える人もいるでしょう。
しかし、議事録は単なる会話の記録ではなく、会議の意思決定や行動の根拠となるビジネス文書です。
だからこそ、きちんと考えながらまとめる力が求められます。
本記事では、どの会社でも議事録を褒められた私が、若手社会人に向けに議事録の取り方を解説します。
議事録の基本、議事メモや発言録との違い、AI活用の注意点、なぜ一度は手動で作成すべきなのかも合わせて解説します。
議事録と議事メモ、発言録の違い
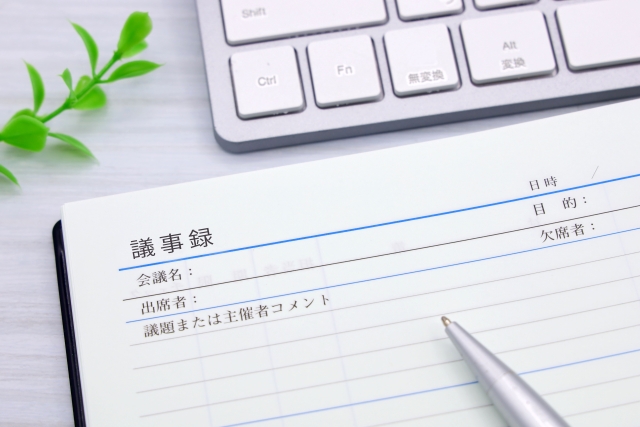
まずは、議事録の基本から押さえましょう。
議事録といっても、実はいくつか種類があります。
大きく分けて3種類あり、議事録、議事メモ、発言録に分けられます。
人によっては、議事メモのことを議事録と言ったり、発言録のことを議事録と呼んでいたりします。
それぞれ混同されやすく、似ているようで目的も内容も違います。
そのため、議事録作成を依頼されたときに、作成すべきものが議事録なのか、議事メモなのか、発言録なのかを見極める必要があります。
作成すべきものを見極めるためにも、それぞれの特徴を押さえましょう。
議事録とは会議での決定事項や結論をまとめた正式な記録
議事録とは、会議の議題、討議の要点、結論、決定事項、アクションアイテムを整理した正式な記録です。
議事録の特徴として、誰が何を言ったかよりも、何が決まったか、次に誰が何をするかが重視されます。
会社の公式記録として保存されることが多い文書です。
上司や関係者が、後から読み返しても内容が分かるレベルでまとめる必要があります。
若手社員がまず最初に任される議事録は、この正式な記録となる議事録を指すことが多いです。
議事メモ
議事メモとは、会議中に自分やチームが必要とする情報を中心に書き留めたメモです。
議事メモの特徴として、自分のために、あるいはチーム内で共有するためにまとめることが多いです。
決定事項以外に、議事録では記載しない雰囲気やニュアンス、上司の一言なども含めやすいです。
議事メモは、特にテンプレートや形式が決まっていないことが多く、どちらかというと、スピードが求められる文書となります。
社会人として、議事録を依頼されていないけど、重要そうな会議だから自分用にまとめておこうという時に便利です。
発言録
発言録とは、会議の発言を一字一句記録したものです。
発言録の特徴は、誰が何を言ったかを忠実に残すことです。
編集せずに、生のやり取りをそのまま残します。
会議の空気感や参加者のスタンスを把握するのに有効です。
「あの会議の時に〇〇さんは何と言っていたっけ?」
「あの会議で××と言っていたのは誰だろう」
発言内容などを後から確認して、言った言っていない問題を解決する時にも有効です。
また、AIの文字起こしツールは、発言録に近いアウトプットを出します。
ただし、ビジネス現場で必要なのは議事録なことが多く、議事録に発言録も付けるなどの使われ方が多いです。
新人のうちに議事録を自分で作成することが重要

「AIがあるならもう手動でやらなくていいのでは?」と思うかもしれません。
しかし、少なくとも社会人として一度は自分で議事録をゼロから作る経験を持つことを強くおすすめします。
議事録を自分で作成することが重要な理由は次の3つです。
- 要点を聞き取る力が身につく
- 会議の流れを俯瞰する力が育つ
- AIで作成した議事録のチェック力がつく
要点を聞き取る力が身につく
議事録を作ると、会議のどこが大事で、どこが雑談かを見分けるスキルが鍛えられます。
見分けるスキルは、営業やプレゼン、商談、報告書作成など、すべてのビジネスシーンに役立つ聞く力です。
議事録を作成する際、どこが決定事項なのか、誰が何を担当するのかといった要点を聞き取り、整理する必要があります。
議事録作成を通して、要点を整理する作業を繰り返すことで、自然と重要な情報を聞き分けるスキルが身につきます。
また、若手社員や新しい環境で仕事を始める場合は、先輩の発言の背景や文脈を考えながら整理することで、会議全体の理解度を深めることもできます。
若手社員が最初にやる仕事として、議事録作成があるのは、会議を通して仕事への理解度を深める目的であることが多いです。
また、AIで議事録を自動生成する場合でも、会議の要点を整理する力が必要です。
AIは、発言をそのまま文字にするのは得意ですが、結論と単なる意見を切り分けが上手く行われないことが多いです。
そのため、AIが作った議事録を確認したり修正したりする必要があり、その際に要点を整理する力が必要になります。
会議の流れを俯瞰する力が育つ
発言をただ追うのではなく、議題 → 議論 → 結論という流れを意識できるようになります。
これは会議運営側に回った時、ファシリテーションや進行管理に直結するスキルになります。
AIを使って議事録を取る場合でも、会議の全体像を正しく把握する必要があります。
会議の議論は必ずしも順序通りに進むとは限りません。
途中で話題が脱線したり、後から重要な結論が出たりすることも多くあります。
そうした会話の断片が並ぶだけでは全体の流れがつかみにくい場合もあります。
そこで、話の始まりから結論までを一本のストーリーに整理することで、会議の流れを俯瞰する力が鍛えられます。
この力は単に議事録作成に役立つだけでなく、業務全般での報告や提案、説明するスキルにも直結します。
AIで作成した議事録のチェック力がつく
AIで作成した議事録を見て、抜けている部分や誤認識してる部分に気づけるのは、自分の手で議事録を作成した経験がある人だけです。
自分で一度やった経験があるからこそ、AIを正しく活用することができます。
AIによる議事録は便利ですが、そのままでは誤字脱字や意味のズレが含まれることも少なくありません。
そのため、最終的に内容を精査し、修正する必要があります。
チェック作業を繰り返すことで、AIが間違えやすいポイントを学び、自然と文章の正確性を見抜く力が身につきます。
たとえば、専門用語が誤変換されやすいことや、話し手が曖昧に表現した部分が要点として抜け落ちやすいことに気づくことができます。
また、AIが生成した文章を、誰が読んでも理解できる表現に直す力も養われます。
単なる校正スキルにとどまらず、自分自身の文章力や説明力の向上にもつながります。
議事録作成の基本的な流れ

ここからは、AIを使わずに自分で議事録を作成する際の流れを説明します。
多くの場合、議事メモや発言録ではなく、議事録の作成を依頼されることが多いので、ここでは議事録の作成の流れを説明します。
議事録作成は、会議に出席している時や会議後だけではなく、会議が始まる前の事前準備も必要です。
会議前、会議中、会議後にそれぞれやるべきことがあります。
会議前にアジェンダ、出欠者確認、テンプレートを準備する
議事録のクオリティは、会議が始まる前の準備で9割決まります。
まず、会議の目的や議題を把握し、アジェンダを確認しておきましょう。
参加者の役職や役割を整理しておくと、発言内容を正確に記録しやすくなります。
さらに、議事録用のテンプレートを事前に用意しておくと効率的です。
テンプレートがない場合は、日時・場所・出席者や議題、決定事項・宿題事項などの枠を作っておけば、会議中に迷わず記録できます。
さらに、日時・場所・出席者や議題も会議が始まる前に記入しておくと、会議内容をスムーズに記録できます。
PCやスピーカーマイク、録音機器、オンライン会議のレコーディング準備も忘れず、スムーズに記録できる環境を整えることが大切です。
会議中のポイント
会議中は「誰が」「何を」「いつまでに」やるかを必ず記録しましょう。
会議中にやるべきことで、重要なのは決定事項(会議中に決まったこと)、責任者(誰がやるのか)、期限(いつまでにやるのか)を正確に残すことです。
全ての発言を記録する必要はありません。
議論の細かいやり取りよりも、結論やアクションプランを簡潔にまとめましょう。
発言者の名前は必要に応じて記載し、誰が何を担当するかが明確になるよう意識します。
また、聞き逃しを防ぐために要点を整理しながらメモをとり、理解が不十分な点はその場で確認する勇気も大切です。
あやふやな発言は後で確認する前提でメモをしておきましょう。
積極的に会議に耳を傾け、後から読み返しても分かりやすい記録を心がけましょう。
会議後に整理
会議が終わったら、できるだけ早く議事録を整理・共有することが重要です。
記憶が新しいうちにまとめれば誤りが少なく、関係者もスムーズに確認できます。
文章は冗長にならないよう簡潔にし、誰が読んでも分かる構成を意識しましょう。
メモもとっていた場合は、清書して決定事項や次のステップが分かる形にまとめます。
最初は大変ですが、何度かやるうちに、ここを押さえておけば大丈夫という勘所が分かります。
共有時はメールや社内ツールを活用し、担当者や期限が明記されているかを再確認します。
また、上司や議長に一度確認してもらうと信頼性が高まります。
迅速かつ正確に配布することで、会議内容が実際の行動に結びつき、チーム全体の成果にもつながります。
AIで議事録を作成する際の注意点

議事録を作成していると、AIで文字起こしすれば楽なのでは?と考える人は多いでしょう。
確かに、AIは人間より速く、会議の内容を文字起こししてくれます。
しかし、議事録にAIを利用する際は、次の3つの点に注意する必要があります。
- 要点を自動でまとめるのがまだ苦手
- 誤認識・聞き間違いリスク
- 情報セキュリティのリスク
要点を自動でまとめるのがまだ苦手
AIを使うと、会議の音声を自動で文字起こししてくれたり、発言を要約してくれます。
しかし現状のAIは、人間のように文脈を理解しながら、本当に重要な要点を抽出することがまだ得意ではありません。
例えば、AIは単に多くの時間を割かれた議論や頻繁に出てきたキーワードを重要と判断する傾向がありますが、実際には短いやり取りの中に重大な意思決定が含まれていることも少なくありません。
決定事項や次のアクションを正確に抜き出すのも難しいです。
その結果、会議の本質が抜け落ちた要約になってしまうリスクがあります。
したがって、AIに要約を任せっぱなしにするのではなく、必ず人が内容を確認し、必要に応じて補足・修正を加える必要があります。
AIはあくまで、たたき台を作る補助ツールと捉え、人間が精査して最終的な議事録を仕上げることが、正確で価値のある記録につながります。
誤認識・聞き間違いリスク
AIによる文字起こしは、常に完璧というわけではありません。
参加者の発音のクセや専門用語、略語、雑音などが原因で誤変換が生じることは珍しくありません。
たとえば「A社」と「衛生」、「仕様」と「使用」のように、発音が似ている言葉が誤認識されると、議事録の内容がまったく異なる意味を持ってしまう可能性があります。
また、複数人が同時に発言した場面では、発言者を誤って認識したり、重要な部分を取りこぼすこともあります。
誤った議事録を公式文書として残すと、後でトラブルの原因になります。
これを防ぐためには、会議の録音環境を整えると良いでしょう。
マイクを近くに置いたり、できるだけ静かな場所で会議を行うと認識精度は向上します。
それでも完全ではないため、最終的には人が校正し、誤字や意味の通らない部分を正しく修正する必要があります。
AIを使えば作業効率は確かに上がりますが、そのままでは誤解を招く可能性があると心得ておくことが大切です。
情報セキュリティのリスク
AIを使って議事録を作成する際に見落とされがちなのが、情報セキュリティの問題です。
クラウド上で音声やテキストを処理するサービスを利用する場合、そのデータがどこに保存され、どのように扱われるかを理解しておく必要があります。
特に、社外秘のプロジェクトや顧客情報が含まれる会議内容を外部のAIサービスにそのままアップロードすると、情報漏洩のリスクにつながります。
また、利用規約によっては、提供したデータがAIの学習に活用される可能性もあります。
これを避けるには、社内で承認されたAIツールを使用すること、データの取り扱いルールを明確に定めることが重要です。
さらに、会議の種類によってはAIを使わず、従来通り人が記録したほうが安全な場合もあります。
まとめ 議事録作成の経験を積んでからAIを活用しよう
今回の記事では、議事録の基本、議事メモや発言録との違い、なぜ一度は手動で作成すべきなのか、AI活用時の注意点を解説しました。
- 議事録は会議の公式文書であり、決定事項とアクションをまとめるのが重要
- AIで作成する議事録は便利だが、誤認識、要点不足、セキュリティのリスクがあるため、人間のチェックと修正が必須
- 議事録の作成すると、聞く力やまとめる力、AI活用力を磨くことができる
AIが普及しても、議事録自分でまとめられる力を持っている人は重宝されます。
なぜなら議事録とは、単なる記録ではなく会議を次の行動につなげるビジネスドキュメントだからです。
議事録を作成し、共有することで、関係者全員で次の行動につなげることができます。
ぜひ、自分の手で議事録を作る経験を積み、その上でAIを活用するスタイルを身につけましょう。