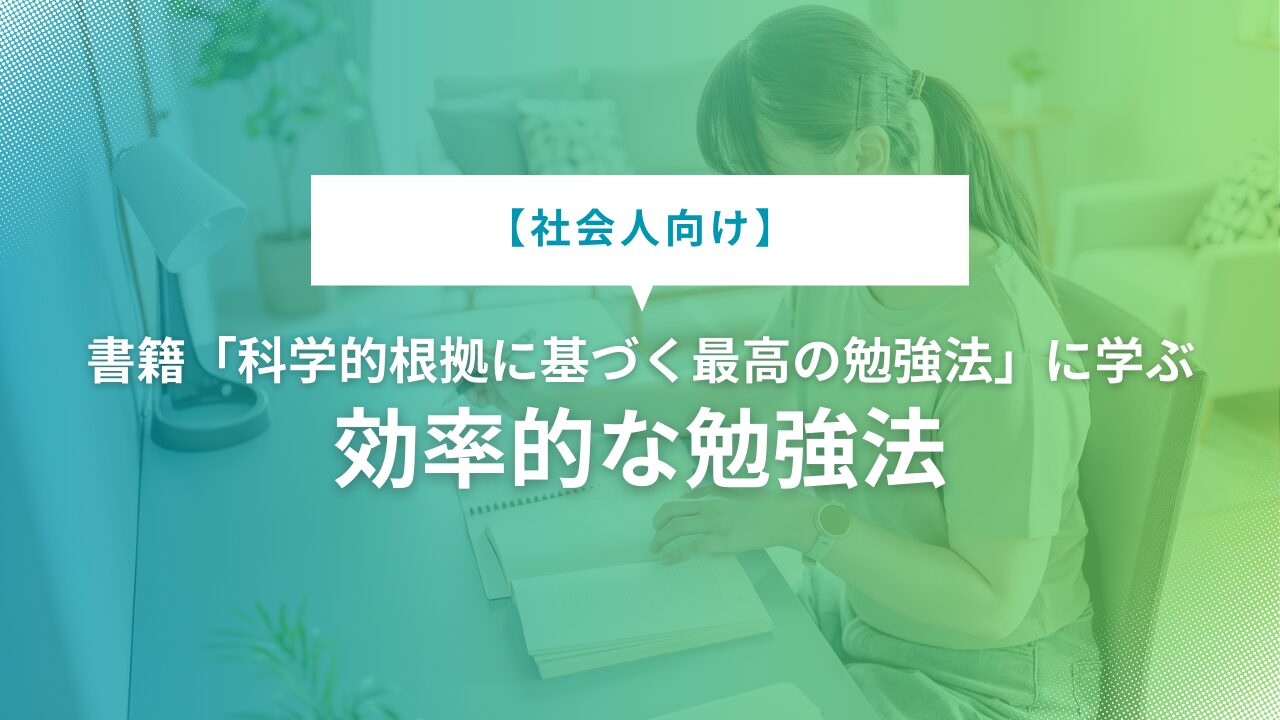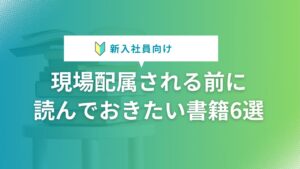資格の勉強をしているけれど、内容がなかなか覚えられなくて困っているんだよね~



国家資格に一発で合格したいけど、どうすれば良いかな?



科学的に有効だといわれている勉強法を学んでいこう!
社会人になると、仕事や家庭などで多忙になり、スキルアップのための勉強時間を確保するのは容易ではありません。
しかし、キャリアアップや資格取得、スキル習得など、社会人になっても何かと勉強が必要なケースが多いでしょう。
場合によっては、昇進や昇格するために資格を取得しなければいけない人もいるかもしれません。
限られた時間の中で成果を出すためには、ただ長時間勉強するのではなく、効率的な学習法を身につけることが重要です。
本記事では、科学的に効果が高い勉強法、低い勉強法、勉強効果を出すための生活習慣などに着目して、効率的な勉強法を紹介します。
書籍「科学的根拠に基づく最高の勉強法」の概要
今回、効率的な勉強法を学ぶために参考にした書籍は、安川 康介「科学的根拠に基づく最高の勉強法」(KADOKAWA)です。
本書は、研究によって有用性が高いあるいは中程度と評価された科学的に効果が高い勉強法と比較的効果が低い勉強法、記憶術、勉強にまつわる環境や自分自身の整え方が紹介されています。
加えて、著者が医師国家資格を合格した時の勉強法も紹介されています。



著者の安川さんは、日本の医師国家試験を受験しながら、アメリカの医師国家試験に上位1%で合格した凄い人なんだ
この記事では触れませんが、本書で紹介されている記憶術は、学生さんはもちろん社会人でも役に立つ記憶術です。
本書もあわせて読んでみてください。
科学的に効果が高い勉強法
科学的に効果が高いとされている勉強法は以下です。
- アクティブリコール
- 分散学習
アクティブリコール
アクティブリコールとは「勉強したことや覚えたいことを、能動的に思い出すこと、記憶から引き出すこと」です。
引用元 安川 康介「科学的根拠に基づく最高の勉強法」(KADOKAWA)
思い出す作業やアウトプットする作業が、記憶を長期に定着させる効果的な勉強法であると、多くの研究で言われています。
アクティブリコールは暗記問題だけでなく、推論などの応用問題にも効果的です。
アクティブリコールは、練習問題を解く、暗記カードを使う、紙に書き出す、学んだことを誰かに教えるなど、様々な方法があります。
満員電車などで参考書や携帯が開けない時は、教科書を読んで学んだことや勉強したことを思い出すのも有効です。
また、調査結果から、アクティブリコールは他の勉強法を比較したときに、勉強の効果が本人では実感しにくいと言われています。
白紙勉強法
著者の方が実践しているアクティブリコールの方法として、白紙勉強法があります。
ブツブツつぶやいて教えるふりをしながら書き出す勉強法です。
用意するもの
・勉強したいもの(教科書、参考書、単語帳など)
・白紙(要らないノートやチラシの裏紙、コピー用紙など)
・書くもの(ペンや鉛筆)
白紙勉強法のやり方
- 教科書や参考書などの覚えたい内容をまず読む
- なにも見ずに、覚えたい内容を白い紙にできるだけ書き出す
後から見返すために書くわけではないので、字は綺麗でなくて良いです - 覚えにくい内容や難しい内容は声に出しながら書く。声に出したほうが記憶に残りやすいと言われています。
- わかっていないこと、忘れていることを、教科書や参考書を見直して内容を確認する
- 2と3を繰り返す
- 時間をおいて、2~4を繰り返す
記憶から引き出す作業を重視し、アウトプット重視の勉強法に変えてみると、より効率的に学習することが可能です。



私も白紙勉強法を試してみて、長期的に記憶が定着するようになりました。
分散学習
試験の前日に暗記科目を集中的にやっても、試験が終わった後は忘れている、という経験ありませんか?
長期的に知識として覚えるためには、一度にまとめて勉強するより時間を空けて繰り返し勉強する必要があります。
時間をあけて勉強することを分散学習といいます。
例えば、2時間勉強するのであれば、続けて2時間勉強するよりも、1時間勉強して別の日にもう1時間勉強した方が、長期的に知識を覚えるには有効です。
分散学習は、幅広い年齢の方に、様々な科目や教材、試験形式において効果が確認されています。
アクティブリコールと分散学習を組み合わせた勉強法を、連続的再学習といいます。
新しい範囲を勉強する際は、1~3回、内容を思い出せるようになるまでアクティブリコールします
連続的再学習を実践するだけで、勉強の効率を大きく改善することが可能です。
科学的に効果が低いとされている勉強法
多くの人がやっているあの勉強法、実は科学的に効果が低いとされている勉強法かもしれません。
時間をかけて勉強しているのになかなか覚えられない人や試験の点数が伸び悩んでいる人は、比較的効果が低いとされている勉強法を実際にやっていないか確認してみてください。
科学的に効果が低いとされている勉強法は以下です。
- 教科書や参考書を繰り返し読む
- ノートに書き写す、まとめる
- ハイライト、下線を引く
教科書や参考書を繰り返し読む
教科書や参考書を繰り返し読むことは、一般的な勉強法に思えます。
しかし、長期的に知識を覚えることを想定した場合、ただ繰り返し読むという勉強法は学習効果が低いとされています。
低いとされている理由は、2回目以降に読んだ時に、1回目よりも文章に見覚えがありスラスラ読めてしまうことで、脳が分かった気になる、理解した気になるからです。
実際には、覚えていなかったり理解していないのに、理解した気になってしまいます。
ノートに書き写す、まとめる
教科書や参考書の内容を、きれいな字でノートに書き写したりカラーペンを使ってまとめたりすることも学習効果が低いとされています。
まとめたりすることで、達成感を感じてしまい勉強した気になってしまうからです。
まとめる(要約)ことは理解する上で重要なことだと思われがちですが、多くの学習者にとっては学習効果が低いとされています。
要約が上手な学習者にとっては効果的とされていますが、多くの方々は要約する訓練が必要だと言われています。
また、授業中にノートをとることは、学習効果はあるが限定的とされています。
ハイライトや下線を引く
単語を覚えるために、教科書や参考書に蛍光ペンで線を引いたりしていませんか?
実は、ハイライトや下線を引くこと自体が、それだけで勉強した気になってしまいます。
そのため、学習効果が低いとされています。
ハイライトや下線を引くのであれば、あとで覚え直すところや参考にできる箇所に線を引くという使い方にすると良いでしょう。
線を引いただけで勉強した気になってしまうことには気を付けつつ、効果の高い勉強法を併せてハイライトや下線を引くようにしましょう。
勉強のモチベーションを高める方法3選
ここまで、科学的に学習効果が低いとされている勉強法と学習効果が高いとされている勉強法を紹介しました。
しかし、いくら学習効果が高い勉強法を知ったとしても、学ぶ意欲がなければ勉強しないので意味がありません。
そこで、勉強のモチベーションを高める方法を3つ紹介します。
- 自己効力感を高める
- 勉強の進捗状況を記録する
- 内発的目標でさらに学習効果を高める
自己効力感を高める
自己効力感とは、「きっと自分ならできる」と目標を達成できると自信を持つことです。
自己効力感が高い人は、勉強に対するモチベーションが高く、より高い目標を設定したり、上手く学習計画を立てることができます。
高い学習成績を出すには、自己効力感を高めることも大切です。
勉強の進捗状況を記録する
勉強をしながら自己効力感を高めるためにも、勉強の進捗状況を記録することは有効です。
自分が勉強した教科の内容、時間、ページ数や時間数を記録することで、パフォーマンスを上げることが可能です。
勉強のモチベーションが上がらない時は、大きな目標を、短期間で達成可能な小さな目標に細分化、自分の進捗を記録。
小さな目標をたくさん達成していくことで、自己効力感が高まり、大きな目標も達成できるようになります。
内発的目標でさらに学習効果を高める
個人の価値観や興味で目標を設定した方が、学習効果を高めることが可能です。
内発的目標とは、個人の価値観や興味で目標を設定することです。
会社からの報酬や承認を目指すのではなく、自己成長やスキルアップなどを目指して目標とすることです。
より勉強したくなるヒント4つ
- インプットは場所を変える
- 勉強しないと後悔することもある
- 好奇心があるときはただ突き進む
- スマホは見えない場所に置く
インプットは場所を変える
試験が控えているとなると、ずっと自宅で勉強するより勉強する場所は変えた方が良いようです。
人は何かを覚える時、知らず知らずのうちに、環境や場所の情報も一緒に覚えています。
覚えた知識を思い出す場所が覚えた場所と異なる場合、複数の異なる場所で情報を入力した方が思い出しやすいことを示唆する報告もあります。
試験会場は知識を覚えた場所と異なるので、試験が控えている場合は、カフェや図書館など様々な場所で勉強するのがオススメです。
集中力が途切れた時に、場所を移動するために歩いたりすることで気分転換になります。
そして、気分転換後にまた集中できるというサイクルを作ることも可能です。
歩くことで運動にもなり一石二鳥です。
勉強しないと後悔することもある
アメリカで行われた調査で、人が最も後悔することの一位が教育・勉強に関することだと報告されています。
機会がああったのにやらなかったことに後悔するといわれています。
何かを学びたいと思っていても、「忙しい」「時間がとれない」など、何かと理由をつけがちです。
ですが、何かを学びたいと考えている人は、後悔しないためにも学び始めることをオススメします。
好奇心がある時は、集中力ややる気があり、知識も覚えやすく、忘れにくいです。
好奇心がある時は、学習にとって有利な状態となります。
好奇心が湧いたら、好奇心に従って勉強してみるのもオススメです。
好奇心に従い勉強することで、勉強自体が楽しくなり、学びたい意欲も向上させることが可能です。
スマホは見えない場所に置く
勉強に集中したいときは、スマホは別の部屋に置いたり、見えない場所に置くようにしましょう。
スマホは、勉強のパフォーマンスに大きく影響するといわれています。
また、スマホは使っていなくても、机上やポケット、カバンにあるだけで脳のパフォーマンスに影響を与えるといわれています。
自分の中で勉強中はスマホを触らない、と決めても、知らず知らずのうちに習慣としてスマホを触り、気づいたらSNSを見ていた、ということもあります。
そのため、見えない場所に置いたほうが良いでしょう。
勉強している途中でも緊急連絡は受け取りたいという方は、電話の通知には気付ける範囲で見えない場所に置いたり、スマートウォッチの活用もおすすめです。
勉強していくなかで不安を感じた時はジャーナリング
「頑張って勉強してきたけれど、合格できないかもしれない」
「時間とお金を使って勉強してきたけれど、失敗したらどうしよう」
国家試験や年に1度しか受験できないような資格の勉強をしていると、不安になることがあるのではないでしょうか。
試験に対して不安や焦りを感じたとき、ジャーナリングをするのがおすすめです。
ジャーナリングとは、ノートなどに頭に浮かんだことや自分の考え、感情をありのままに書き出すことです。
特に悩んでいる場合は、著者がやっている以下の手順で、ジャーナリングをすすめると有効です。
ジャーナリングの進め方
- 悩んでいる事柄を詳しく書き出す
- それについて、自分にできることを書き出す
- どうするかを決める
- 決めたことをやる
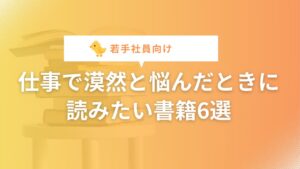
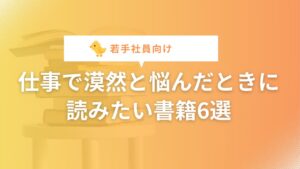
まとめ 科学的に学習効果が高い勉強法を実践してスキルアップしよう
今回は、科学的に学習効果が高い勉強法と低い方法、勉強するモチベーションを高くする方法を紹介しました。
学習効果が高い勉強方法は次の4つです。
- アクティブリコール
- 分散学習
勉強のモチベーションを高める方法と、より勉強したくなるようなヒントも紹介しました。
スキマ時間などを活用しながら、効率的に勉強することでスキルアップしていきましょう。